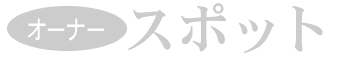
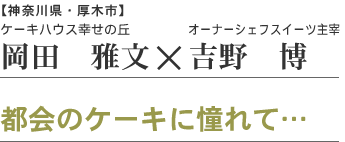
吉野
生年月日とご出身地を教えてください。
岡田氏
生まれは1949年の1月21日です。
出身地は四国高知県の四万十川の近くです。
吉野
雄大な自然が溢れるところですね。
岡田氏
見渡す限り山と川でした。
友達と暗くなるまで山や川で遊びました。山では山芋堀りでしたし、川では鮎やうなぎを捕まえていました。ご飯のおかずになりますので家の為になるものを採ってたね。
吉野
遊びが家の役に立っていたんですね。小学校の頃好きだった科目とか教科とかありましたか?

岡田氏
身体を動かす事が好きだったので体育かなぁ・・・・。
吉野
岡田オーナーの幼い頃には、テレビがあった時代ではないですね?
岡田氏
そうですね。一般家庭にはテレビなんてなかったねぁ・・・。
10歳の頃に近くの家がテレビを買ったんで学校の友達と一緒に観に行ってました。テレビがある家が珍しい頃だったんでプロレスや野球があるとその家は入りきれないくらいに近所の人が集まったね。
吉野
何か熱中してた事はありますか?
岡田氏
中学から野球をやりだして熱心にやっていました。早朝野球は今でも続けています。
吉野
菓子職人になるキッカケって何だったんですか?
岡田氏
親戚が高知の中村市って所で駄菓子屋をやってたんで、菓子職人でもやってみたらと言われまして、私も甘いものが好きだったんで深い考えもなく中学を出てすぐに高知市にある「浜幸」という和洋菓子を作っている大きな会社に就職しました。
吉野
菓子修行は大変でしたか?
岡田氏
う〜ん・・・・大変という気持はなかったなぁ。仕事をやる事に関しては言われた通りの事を真面目にやってましたね。
最初は洗い物ばかりでした。しばらくすると和菓子職人が丸めた生地をお菓子の型に入れて鉄板の上に並べるという仕事です。
洋菓子にさわれるのはクリスマスの時のデコレーションの飾りつけだけでした。
吉野
そこには何年おられたんですか?
岡田氏
2年間です。お菓子作りが機械化されてきた時期だったんで嫌になって辞めてしまいまして、高知市の和菓子を作っていた個人店に入りました。丁度その頃に東京の洋菓子店で修行していた方が高知市に洋菓子店をオープンされたんです。
そこのオーナーが作るケーキが都会的で一目見ただけで憧れてしまいました。和菓子屋の仕事が終わると毎日ケーキを見に通いました。
東京に洋菓子の修行に行きたいという気持が日増しに高まってきたんです。
自分としては菓子職人として店を出したいという気持があって、その洋菓子店のお菓子を見てこういうお菓子を作る店を出したいと思っていましたね。
吉野
そういう気持になると、もう和菓子どころではないですね。
岡田氏
そうなんです。和菓子屋の親方には申し訳なかったんですが、思い切ってその洋菓子店のオーナーに東京の洋菓子店を紹介してくれって頼んだんです。
吉野
紹介していただけたんですか?
岡田氏
ええ、東京の小金井にある店を紹介してもらいました。
吉野
ご両親は心配されたのではないですか?
岡田氏
うちの実家から高知まで3時間はかかるんです。だから、当時東京に行くという事は今で言えば外国に行くような感覚でした。
だから両親も心配すると思っていたので手紙で知らせただけでした。
吉野
どうでした東京の洋菓子店は?
岡田氏
実際にその店に行ってみるとチーフが独立して店を辞めるので神奈川の別の洋菓子店を紹介されたんです。
吉野
どういう事ですか?
岡田氏
高知の洋菓子店のオーナーが私を店のオーナーに紹介したのか、店のチーフを紹介したのかは分かりませんが、チーフからそう言われたので訳も分からずに厚木に行ったんです。
吉野
何という洋菓子店ですか?
岡田氏
サンベリナという洋菓子専門店で職人が8人いました。
吉野
本格的に洋菓子店での仕事ですが、いかがでしたか?
岡田氏
最初は戸惑いもありましたが、親切に教えてくれたので仕事はすぐに覚える事ができました。
ただ、高知では朝の7時から仕事をして夕方の5時くらいには終わっていたんですが、サンベリナではとにかく忙しかったですね。
朝7時から夜の11時まで仕事でした。
その当時 昭和43年頃は、洋菓子は作ればその場で売れる時代でしたんで作っても作っても足りませんでした。でも私としては作るケーキがお洒落で都会的なセンスのものばかりだったんでそれを作るのが嬉しかったなぁ。
吉野
当時はバタークリームですか?
岡田氏
いえ、生クリームが入って来て、それが主流になりつつある時代でした。
初めて生クリームを食べた時には、こんな美味しいクリームがあるのかってほど感動したのを覚えているなぁ・・・・。
吉野
サンベリナでは何年間勤められたんですか?
岡田氏
5年間です。26歳の時でした。それから独立です。
吉野
26歳の若さで自分の店を持ったんですか?少し早いんではないのですか?
岡田氏
「サンベルナ」の社長も心配して「やれるのか?」と聞いてきたけど、そう言われると店をやれる自信はあった訳ではなかったけど「え〜い、やっちゃえ!」という勢いだけで店を始めました。
吉野
店名の「幸せの丘」ってどういう意味合いで付けられたんですか?
岡田氏
座間駅の近くで始めたんですが、駅から坂を登った所にあったんで「丘」というイメージだったんです。
それとケーキを食べて幸せになってもらいたいという気持もあって「幸せの丘」という店名にしました。
当時の洋菓子店は、フランス語などの横文字の店が多かったんだけど、自分の店のお菓子はフランス菓子というものではなかったんで分かり易い名前がいいかなと思ったんです。
吉野
最初は、何人で始められたんですか?
岡田氏
製造は、私と菓子職人がひとり、販売はパートさんでスタートでしたよ。
吉野
売上はどうでした?
岡田氏
座間で最初の洋菓子屋だったんで売れに売れましたね。寝る暇もないほど忙しかったね。
店は、お子さんから年配の方まで気軽に食べてもらえるような商品にしたし、値段もできるだけ安くという方針でやっていたから、
それが、良かったんでしょうね。
吉野
当時は、洋菓子店がない場所ってまだまだあったんですね。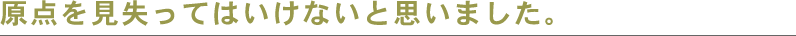 岡田氏
岡田氏
現在では、考えられないけどあの頃はそうだったね。
でも、何年か経ってくると洋菓子店が増えてきて、それまでのように作れば売れるという事はなくなってくるので、お菓子の講習会に積極的に参加して菓子作りを学んでは、新しいケーキを出してお客様に飽きられないように努力はしましたね。
独立してからが本当の勉強だったね。
吉野
その頃は、どこにお住まいだったんですか?
岡田氏
厚木に住んでいたんで座間まで毎日通っていました。
吉野
そんなには離れていないですね。
岡田氏
距離はそう遠くはないんだけど車で通ってたんで朝とか混んで時間はかかるし、座間の店は10坪しかなくて手狭になっていたし、もっと近い所に職場があれば楽だなと思って、座間でやって8年目かな・・・厚木に支店を出したんです。
吉野
どうでした厚木支店の売上は?
岡田氏
思ったより売れなかった。最初つまずいたね。
吉野
何か理由があったんですか?
岡田氏
あの頃は、バブル景気の時代で小さくて値段が高いケーキが流行ってたんで、そういうケーキにしたのが間違いだったんだね。
小さいお子さんから年配の方まで気軽に来れる店という原点を見失ってしいたんだね。それに気付いてケーキを大きくして値段も下げたら盛り返して売れ出したんですよ。
吉野
なるほど時代の流れも大切ですけど、店の原点は変えてはいけないという事ですね。
岡田氏
そうです。それを痛感したね。自分の原点の小さなお子さんから年配の方々まで気軽に来ていただける店というのは、突き詰めて言うと「美味しい、大きい、安い」なんですよ。だから、この部分は絶対変えたらいけないと思いましたね。
吉野
そうですね。今ではコンビニやスーパーにもそれなりに美味しいスイーツが安く売っている時代ですからね。
岡田氏
家庭を持っているサラリーマンだったら1個500円のケーキは無理ですよね。
ホテルのディナーの後のデザートならたまには贅沢して高いものもいいかなと思うけど、普段ケーキを食べたいと思ったら1個500円も600円もするケーキは買わない。
フランスに行って修行して珍しい材料で手の込んだお菓子を提供する店ならそれなりの値段になるのはしょうがないけど、私らみたいに地域に密着している菓子屋は、美味しさや安さを一番に考えないといけないと思いましたね。
吉野
そうですね。地域ごとでお菓子に対する考え方は違いますからね。
岡田氏
都内の店だったら個性を持たないとつまらないし、お客様は、その個性的なお菓子を求めて来られると思うんだけど。私たちの店とは、求められる意味合いが違うと思うんですよ。

吉野
岡田オーナーがオーナーシェフの店に求められる部分というのは商品の大きさや安さ以外に何だとお考えですか?
岡田氏
鮮度です。駅にテナントで出店しているチェーン展開の洋菓子店に私らのオーナーシェフの店みたいに焼きたて作りたてを提供する事は物理的にできませんよ。
吉野
やはりオーナーシェフの店は、新鮮さで勝負ですね。
岡田氏
そうです。鮮度の美味しさには勝てないと思いますね。だから、それを一番に大事にしていきたいし、それがオーナーシェフの最大のメリットだと思いますね。そこが、私らが勝負できる所だよね。
吉野
現在の店舗は、いつオープンされたんですか?
岡田氏
1995年 平成7年ですね。座間も厚木の支店も全て閉めて、ここ1店舗でやることにしました。
吉野
菓子職人にとって大切な事はなんですか?
岡田氏
基本が大切。まず基本をキッチリおさえないといけない。その上で自分なりの工夫をしていく事が大切だよね。
焼くときは20分焼くところを あと1分焼いたらどうなるのかという研究も必要だよね。
基本を押さえた上で、同じ商品でも進化させていくとう事もやっておかないといけないと思いますねぇ。そういう地味な積み重ねをやることが大切だと思いますよ。
菓子職人というのは、一攫千金という発想ではできない。毎日コツコツやるしかないという事ですよ。
吉野
パティシエになる方々へのアドバイスをお願いします。
岡田氏
辛抱。辛抱しないといけない。
私たちの仕事は農家の方と同じですよ。農家の方は、作物を収穫するまで畑に種を植え、雑草を刈り、肥料をまき、水をやり・・・と毎日コツコツ仕事をしている。私たちもお菓子の材料を合わせ窯に入れ、ひとつひとつのお菓子を手作りしていくという地味な仕事。
それが毎日だから気持が乗らないとか身体の調子が悪いとあるんですよ。
でもね休むわけにはいかない仕事だから、もう毎日地道にやるしかない。どんなコンディションの悪い時でも辛抱してやるしかないんだよね。
それが、できるかできないか・・・。できなければ菓子職人にはならないほうがいいと思いますよ。毎日お客様の期待を裏切らない美味しいものを作るってそういう事です。 でもね、何の為に辛抱するのかというとお客様から「美味しかった」と言ってもらえる事が嬉しいからなんですよ。
だから私もお客様の「美味しい」という一言があるから元気をもらえて、毎日辛抱してやっていけてるんですよ。
吉野
今日は、貴重なお話ありがとうございました。
身体を動かす事が好きだったので体育かなぁ・・・・。
吉野
岡田オーナーの幼い頃には、テレビがあった時代ではないですね?
岡田氏
そうですね。一般家庭にはテレビなんてなかったねぁ・・・。
10歳の頃に近くの家がテレビを買ったんで学校の友達と一緒に観に行ってました。テレビがある家が珍しい頃だったんでプロレスや野球があるとその家は入りきれないくらいに近所の人が集まったね。
吉野
何か熱中してた事はありますか?
岡田氏
中学から野球をやりだして熱心にやっていました。早朝野球は今でも続けています。
吉野
菓子職人になるキッカケって何だったんですか?
岡田氏
親戚が高知の中村市って所で駄菓子屋をやってたんで、菓子職人でもやってみたらと言われまして、私も甘いものが好きだったんで深い考えもなく中学を出てすぐに高知市にある「浜幸」という和洋菓子を作っている大きな会社に就職しました。
吉野
菓子修行は大変でしたか?
岡田氏
う〜ん・・・・大変という気持はなかったなぁ。仕事をやる事に関しては言われた通りの事を真面目にやってましたね。
最初は洗い物ばかりでした。しばらくすると和菓子職人が丸めた生地をお菓子の型に入れて鉄板の上に並べるという仕事です。
洋菓子にさわれるのはクリスマスの時のデコレーションの飾りつけだけでした。
吉野
そこには何年おられたんですか?
岡田氏
2年間です。お菓子作りが機械化されてきた時期だったんで嫌になって辞めてしまいまして、高知市の和菓子を作っていた個人店に入りました。丁度その頃に東京の洋菓子店で修行していた方が高知市に洋菓子店をオープンされたんです。
そこのオーナーが作るケーキが都会的で一目見ただけで憧れてしまいました。和菓子屋の仕事が終わると毎日ケーキを見に通いました。
東京に洋菓子の修行に行きたいという気持が日増しに高まってきたんです。
自分としては菓子職人として店を出したいという気持があって、その洋菓子店のお菓子を見てこういうお菓子を作る店を出したいと思っていましたね。
吉野
そういう気持になると、もう和菓子どころではないですね。
岡田氏
そうなんです。和菓子屋の親方には申し訳なかったんですが、思い切ってその洋菓子店のオーナーに東京の洋菓子店を紹介してくれって頼んだんです。
吉野
紹介していただけたんですか?
岡田氏
ええ、東京の小金井にある店を紹介してもらいました。
吉野
ご両親は心配されたのではないですか?
岡田氏
うちの実家から高知まで3時間はかかるんです。だから、当時東京に行くという事は今で言えば外国に行くような感覚でした。
だから両親も心配すると思っていたので手紙で知らせただけでした。
吉野
どうでした東京の洋菓子店は?
岡田氏
実際にその店に行ってみるとチーフが独立して店を辞めるので神奈川の別の洋菓子店を紹介されたんです。
吉野
どういう事ですか?
岡田氏
高知の洋菓子店のオーナーが私を店のオーナーに紹介したのか、店のチーフを紹介したのかは分かりませんが、チーフからそう言われたので訳も分からずに厚木に行ったんです。
吉野
何という洋菓子店ですか?
岡田氏
サンベリナという洋菓子専門店で職人が8人いました。
吉野
本格的に洋菓子店での仕事ですが、いかがでしたか?
岡田氏
最初は戸惑いもありましたが、親切に教えてくれたので仕事はすぐに覚える事ができました。
ただ、高知では朝の7時から仕事をして夕方の5時くらいには終わっていたんですが、サンベリナではとにかく忙しかったですね。
朝7時から夜の11時まで仕事でした。
その当時 昭和43年頃は、洋菓子は作ればその場で売れる時代でしたんで作っても作っても足りませんでした。でも私としては作るケーキがお洒落で都会的なセンスのものばかりだったんでそれを作るのが嬉しかったなぁ。
吉野
当時はバタークリームですか?
岡田氏
いえ、生クリームが入って来て、それが主流になりつつある時代でした。
初めて生クリームを食べた時には、こんな美味しいクリームがあるのかってほど感動したのを覚えているなぁ・・・・。
吉野
サンベリナでは何年間勤められたんですか?
岡田氏
5年間です。26歳の時でした。それから独立です。
吉野
26歳の若さで自分の店を持ったんですか?少し早いんではないのですか?
岡田氏
「サンベルナ」の社長も心配して「やれるのか?」と聞いてきたけど、そう言われると店をやれる自信はあった訳ではなかったけど「え〜い、やっちゃえ!」という勢いだけで店を始めました。
吉野
店名の「幸せの丘」ってどういう意味合いで付けられたんですか?
岡田氏
座間駅の近くで始めたんですが、駅から坂を登った所にあったんで「丘」というイメージだったんです。
それとケーキを食べて幸せになってもらいたいという気持もあって「幸せの丘」という店名にしました。
当時の洋菓子店は、フランス語などの横文字の店が多かったんだけど、自分の店のお菓子はフランス菓子というものではなかったんで分かり易い名前がいいかなと思ったんです。
吉野
最初は、何人で始められたんですか?
岡田氏
製造は、私と菓子職人がひとり、販売はパートさんでスタートでしたよ。
吉野
売上はどうでした?
岡田氏
座間で最初の洋菓子屋だったんで売れに売れましたね。寝る暇もないほど忙しかったね。
店は、お子さんから年配の方まで気軽に食べてもらえるような商品にしたし、値段もできるだけ安くという方針でやっていたから、
それが、良かったんでしょうね。
吉野
当時は、洋菓子店がない場所ってまだまだあったんですね。
現在では、考えられないけどあの頃はそうだったね。
でも、何年か経ってくると洋菓子店が増えてきて、それまでのように作れば売れるという事はなくなってくるので、お菓子の講習会に積極的に参加して菓子作りを学んでは、新しいケーキを出してお客様に飽きられないように努力はしましたね。
独立してからが本当の勉強だったね。
吉野
その頃は、どこにお住まいだったんですか?
岡田氏
厚木に住んでいたんで座間まで毎日通っていました。
吉野
そんなには離れていないですね。
岡田氏
距離はそう遠くはないんだけど車で通ってたんで朝とか混んで時間はかかるし、座間の店は10坪しかなくて手狭になっていたし、もっと近い所に職場があれば楽だなと思って、座間でやって8年目かな・・・厚木に支店を出したんです。
吉野
どうでした厚木支店の売上は?
岡田氏
思ったより売れなかった。最初つまずいたね。
吉野
何か理由があったんですか?
岡田氏
あの頃は、バブル景気の時代で小さくて値段が高いケーキが流行ってたんで、そういうケーキにしたのが間違いだったんだね。
小さいお子さんから年配の方まで気軽に来れる店という原点を見失ってしいたんだね。それに気付いてケーキを大きくして値段も下げたら盛り返して売れ出したんですよ。
吉野
なるほど時代の流れも大切ですけど、店の原点は変えてはいけないという事ですね。
岡田氏
そうです。それを痛感したね。自分の原点の小さなお子さんから年配の方々まで気軽に来ていただける店というのは、突き詰めて言うと「美味しい、大きい、安い」なんですよ。だから、この部分は絶対変えたらいけないと思いましたね。
吉野
そうですね。今ではコンビニやスーパーにもそれなりに美味しいスイーツが安く売っている時代ですからね。
岡田氏
家庭を持っているサラリーマンだったら1個500円のケーキは無理ですよね。
ホテルのディナーの後のデザートならたまには贅沢して高いものもいいかなと思うけど、普段ケーキを食べたいと思ったら1個500円も600円もするケーキは買わない。
フランスに行って修行して珍しい材料で手の込んだお菓子を提供する店ならそれなりの値段になるのはしょうがないけど、私らみたいに地域に密着している菓子屋は、美味しさや安さを一番に考えないといけないと思いましたね。
吉野
そうですね。地域ごとでお菓子に対する考え方は違いますからね。
岡田氏
都内の店だったら個性を持たないとつまらないし、お客様は、その個性的なお菓子を求めて来られると思うんだけど。私たちの店とは、求められる意味合いが違うと思うんですよ。

吉野
岡田オーナーがオーナーシェフの店に求められる部分というのは商品の大きさや安さ以外に何だとお考えですか?
岡田氏
鮮度です。駅にテナントで出店しているチェーン展開の洋菓子店に私らのオーナーシェフの店みたいに焼きたて作りたてを提供する事は物理的にできませんよ。
吉野
やはりオーナーシェフの店は、新鮮さで勝負ですね。
岡田氏
そうです。鮮度の美味しさには勝てないと思いますね。だから、それを一番に大事にしていきたいし、それがオーナーシェフの最大のメリットだと思いますね。そこが、私らが勝負できる所だよね。
吉野
現在の店舗は、いつオープンされたんですか?
岡田氏
1995年 平成7年ですね。座間も厚木の支店も全て閉めて、ここ1店舗でやることにしました。
吉野
菓子職人にとって大切な事はなんですか?
岡田氏
基本が大切。まず基本をキッチリおさえないといけない。その上で自分なりの工夫をしていく事が大切だよね。
焼くときは20分焼くところを あと1分焼いたらどうなるのかという研究も必要だよね。
基本を押さえた上で、同じ商品でも進化させていくとう事もやっておかないといけないと思いますねぇ。そういう地味な積み重ねをやることが大切だと思いますよ。
菓子職人というのは、一攫千金という発想ではできない。毎日コツコツやるしかないという事ですよ。
吉野
パティシエになる方々へのアドバイスをお願いします。
岡田氏
辛抱。辛抱しないといけない。
私たちの仕事は農家の方と同じですよ。農家の方は、作物を収穫するまで畑に種を植え、雑草を刈り、肥料をまき、水をやり・・・と毎日コツコツ仕事をしている。私たちもお菓子の材料を合わせ窯に入れ、ひとつひとつのお菓子を手作りしていくという地味な仕事。
それが毎日だから気持が乗らないとか身体の調子が悪いとあるんですよ。
でもね休むわけにはいかない仕事だから、もう毎日地道にやるしかない。どんなコンディションの悪い時でも辛抱してやるしかないんだよね。
それが、できるかできないか・・・。できなければ菓子職人にはならないほうがいいと思いますよ。毎日お客様の期待を裏切らない美味しいものを作るってそういう事です。 でもね、何の為に辛抱するのかというとお客様から「美味しかった」と言ってもらえる事が嬉しいからなんですよ。
だから私もお客様の「美味しい」という一言があるから元気をもらえて、毎日辛抱してやっていけてるんですよ。
吉野
今日は、貴重なお話ありがとうございました。